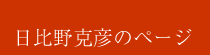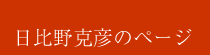|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
このごろ、よく考える。自分の存在について。
チラシは新聞のおまけなのだろうか。
そんなこと、と思うかもしれない。でも、チラシにとっては生死にかかわる重大な問題なのだ。いつもは主役の座を奪われているような気がする新聞になりすまして、チラシのことを考えてみたい。
そもそも、わがチラシの元祖は江戸の呉服商だった三井越後屋の「現金安売掛値なし」という引き札。1683年、天和3年に現れた。かわら版はそれを遡ること68年、1615年に大阪で夏の陣のことについてふれたものが始まり、といわれる。悔しいが、登場からチラシは新聞に先を越された。それでも、十返舎一九や滝沢馬琴、平賀源内たち超一流の戯作者がコピーライターで、子孫の自分が言うのも何だが、独立独歩のなかなかのチラシだった。
ところが明治に入って、新聞が勝手に「チラシを付録として配布する」と読者にのたまい、チラシはすべてではないが、新聞と合流した。でも、そこでめげないのが、われわれの祖先のいいところ。チラシは新聞にはできないアピールを始めた。読まれることより見られることを重視し、多彩
に、そして多様に変身した。例えば、型抜きされたものや電報型、子どものお面や団扇にも化けたり、アイディアが満載された“作品”のようだった。
第二次世界大戦後、高度成長とともにチラシは人々に広く認知されるようになり、スーパーが出現したころから仲間は大勢増えた。しかし増えれば増えるほど単なる店や商品の広告紙化し、ちらり見て捨てられる無個性な存在になり、チラシ自身、新聞のおまけであることに疑問を持つこともなくなった。いま、北海道では新聞からチラシが消え、代わりに毎日、フリーペーパーが家庭に届けられているという。とにかく、とにかくチラシの身は危うい。
そんな時、アーティストのヒビノが「コンセプトチラシ」なるものを、突然、言い出した。ある1つのコンセプトを設定し、まちを歩いて商品をセレクトして広告する手書きチラシ。「これは何か、再生の手がかりになるかもしれない」。そうピーンときた。真面
目に言えば、原点に立ち返って、納得した進化ができるのではないかと思った。ヒビノはその可能性を見つける手法を教えてくれた気がする。
チラシのこけんにかけて言う。
チラシは新聞のおまけではない。チラシはチラシであって、新聞にはないのびやかな感性と視点、独特のメッセージがある。必ず、それを追求してみせる! |
|
|
|