



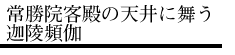 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 迦陵頻伽(かりょうびんが)。上半身が菩薩、下半身が鳥、両翼それに天衣をまとい、音を奏でる。いわき市平愛谷町の紋章上絵師で画家の石川貞治さん(54)はその迦陵頻伽を、改修していた常勝院=平中平窪=の客殿の天井画に描いた。仏画も天井画も、縦3.6メートル、横6.3メートルという大きさも、初めてのこと。依頼があって2年、制作に入って1年かかって完成した迦陵頻伽は天に舞い、美しい音楽を奏で、華をまき散らす。 | |
|
キャンバスは未知数の素材、ラオスヒノキ。30センチ幅の21枚の板の到着を待って、昨年2月から常勝院のそばの建物をアトリエに制作に取りかかった。色づきをよくするために、まずワイヤーブラシで表面
をたたいて細かい穴をあけて、それから、にかわで練った糊粉を塗って白い画面にした。 制作している間、この道でいいのかどうかわからないまま何日か夜道を歩いている感覚があった。作品があまりに大きすぎて、描いたものの位置に目が置けず、全体像が見えていないかもしれない、と思ったという。本来なら50メートルぐらい離れたところから眺めてみなければならないが、いつも斜めから見ている感じがした。 常勝院では現在、参道の工事なども行われていて、一般の人が迦陵頻伽を見られるのは6月から。いわきの寺にいわきの画家が描いた天井画。いわきの宝物が1つ増えた。 |
│日々の新聞│風の通 る家│いわきクロニクル│オンブズマン│情報│
│編集後記│田人お伽草紙│草野天平の頁│日比野克彦のページ│
│フラガール│オリジナルショップ│定期購読│リンク集│
