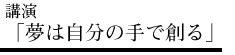|
建築家・安藤忠雄さんの講演会(いわき建築設計事務所協会主催)が4月24日、いわき市文化センターで開かれた。安藤さんはスライドを使いながら、自らの生い立ちや建築に対する思いなどを大阪弁で話し、600人の聴衆を安藤忠雄の世界に引き込んだ。
はじめに巻さんから絵本美術館の仕事の依頼が来ました。「福島は遠いなぁ、やめとこ」。正直そう思いました。でも、手紙を読んで「30年も自分の夢を温めてる」、というところに引っかかりました。しかし、ほんま遠いですなぁ。空港から1時間半もかかるんですから。えらいとこへ来てしまった、というのが実感です。
学歴社会が崩れてきた、とはいえ依然として学歴社会は存在していますし、地方の時代だと言っても東京一極集中は変わっていません。私も地方の人間です。大阪は言ってみれば大きな地方都市なんです。私は祖母に育てられました。工業高校を卒業するときに、大学進学という選択もないことはなかったんやけど、経済的な理由と学力の問題で断念したんです。お金がなくて行けるところは大阪大学の建築ぐらいしかありませんでしたから、難しかったんです。そして必要なら働きながら学べばいい、と思いました。
そのとき祖母はこう言いました。「どっちみちお前の人生はうまくいってない。だから何をやってもいい。ただ、あきらめるな。そして社会に迷惑をかけるな。それ守れるんやったらなにやってもええ」。だからよく言うんです。「一流大学へ行けなかったからといって、それは挫折やない。がんばれば大丈夫。でも本当にがんばらんとあかんよ」って。
私は大阪に義理があります。社会基盤も学歴もない、まだ若いときに25坪の家を任せてくれた人がおったんです。そして少しずつ仕事をするようになってある年齢になったら、サントリーの佐治敬三さんやら、京セラやサンヨーなど経済界のおえらいさんたちが「安藤さんはおもしろいから、生涯青春を生きなさい」と言ってくれました。そして、1996年(平成8年)、東大から教授として来て、という話があったんです。
すると佐治さんたちは「やめなさい」と言う。「大阪におってこそ大阪人なんやから。東大は高卒なんて認めちゃいない。博士号がないと…。そんなつまらんことやめといたら」って。「分相応じゃないよ」と言ってくれたんでしょうな。それでも「学ぶということに参加したい」と言うたんです。そしたら、東大の先生方を大阪に呼んで飲ませた。接待したんです。どんどん飲ませて「これで大丈夫や。接待受けたんやから」って言うて東京へ送り出してくれました。そして東大では学生たちにいろいろ教えてもらいました。
どうして子どもの施設をつくるか?ですが、少子化、高齢化のなかで子どもたちに自由に元気に育ってほしい、と願うからなんです。朝から晩まで塾に行って一流大学へ入る。それも必要かもしれません、でも子どものときに見た風景や体験というものは必ず残るんです。詰め込みと自由、子どもにとってはどちらも大事なんです。
いつだったか、雨の日に若者がバケツに水を入れて木のそばにやってきました。「それどうすんの?」と尋ねると、「木にかけるんです」と言う。「だって雨降ってるよ。いいんとちゃう」と言うと、「決まりですから」。木はぎりぎりまで水をやらない方がいいんです。水をかけすぎると腐ってしまうんです。子どもも同じで、ぎりぎりまで手を差しのべないことが大事なんです。自分で判断できる次世代の子どもたちをしっかり育てていかないと、いかんと思うんです。
絵本美術館は美術館と言うよりは図書館のようなものなんですが、子どもたちが自分の場所を自分で考えられるように、自分の場所を見つけられるようにしてほしい、と思って設計したんです。ただ単に箱をつくるのではなくて思いがいっぱいある建物、言葉じゃなくって心の話ができ、心を動かされる建物にしたい、と思いました。
建築とは社会との関わり合いなんです。社会は1人ではできません。みんなつながっているんです。そうしたなかで自分の仕事に情熱と責任感を持って生きていくことが大事なんです。そして自分の責任とは、祖母が言うてくれた「人に迷惑をかけるな。責任を守れ」ということです。
え、私の夢ですか? そうやなぁ、自分が造った建物や環境がその後どんなふうになっているか、それを見て歩きたいですね。
|